業務の創造化
0pt

「事業の創造化」を現場目線の「業務の創造化」として捉え、定義、求められる理由、効用を解説していく。
「業務の創造化」とは何か
あらゆる業務は創造的と定型的の2面を持っている。定型的とはいわゆるマニュアル業務であり、完了までの時間はまちまちだが漏れなく進めれば終了する。業務遂行において個人の能力が寄与する割合は熟練のみである。
一方で創造的な業務とは、誰も手がけたことがなく、そもそも行うことが必要かどうかすらわからない。完成までにどの程度の時間がかかるか不明な一方で、有限の時間内に効果を生み出さないと無意味となってしまう。業務遂行において個人の能力が寄与する割合は高く、その種類も無限である。
これは事業におけるコンセプトの追求か、それともコンセプト自体の創造かと密接に連動している。
以下に定型的、創造的の度合いに応じた業務例とKPIを4パターン挙げる。
定型的な性格の強い業務
ラインでの組み立て業務、伝票処理業務などがある。
共通する要素は反復性の高さが挙げられる。
KPIは今の生産性の高さであり、対固定費のパフォーマンスが求められる。
定型的だが創造的な性格を持つ業務
定常状態で遂行しているダイヤモンドマトリクスの業務である。
顧客との価格交渉、コールセンターでの対応、伝統的な保守サポートなどがある。
共通する要素は個別対応が不可欠だが、シナリオ自体は既に作られていることである。
KPIはPL管理が基本だが、CSの充実などの非財務的なパフォーマンスもペアで求められる。
創造的だが定型的な性格も持つ業務
トヨタ方式の「カイゼン」やシステム(組織体系も含む)の再編などがある。
共通する要素はバリューチェーンをまたいだ最適化の実現である。
KPIはキャッシュフローの改善であるため、隠れたKPIにリストラクチャリングが隠れていることもある。
創造的な性格の強い業務
新たな事業戦略の立案、組織横断的な情報収集やコラボレーションなどがある。
共通する要素は状況を支配する構造の変化を引き起こすことである。
KPIは効果的な新指標の定義であり、柔軟性、迅速性による投資効果の最大化である。
何故「業務の創造化」が求められるか
事業を行う上で業務の効率化は不可避である。効率化の方法としては2つあり、連続的な効率化と不連続な効率化である。実際に採用される効率化は連続的な効率化が圧倒的である。
連続的な効率化が採用される理由
理由は導入トラブル発生時の事業リスクにある。いくつかの業務パラメータを変更するだけであれば、生産性を損なうことなく移行ができるし、変更後に不都合が発生してもそのパラメータだけを元に戻せば済む。一方で不連続な効率化を追求する場合、不可逆のため変更には時間がかかる上、一時的に生産性は下がる。更に変更後に不都合が発生した際は更に時間をかけて元に戻す必要があるので、更に事業インパクトが大きくなる。
連続的な効率化を採用し続けることで失われる将来の競争力
一方で見落としがちなのは、将来にわたった価値の提供で見た場合、正反対の結果となることである。つまり不連続な効率化を採用するほうが、現場としては連続の効率化よりも苦しい反面、将来の業務は先鋭的なものとなる。また経営観点でみると実現リスクは高いが、将来における事業の投資効果は高くなる。
「業務の創造化」により確保する将来の競争力につながる本質
現在のように変化の激しい時代において連続的な効率化のみで事業を運用しようとするならば、極めて短時間で事業を回す業務の効率化を達成しなければならない。しかし実現には場当たり的となり、非効率な投資となるため、結局は業務漁の肥大化と事業としての限界に直面することとなる。
このために追求する本質が「業務の創造化」である。
「業務の創造化」を実現するにはどうするか。
業務の創造化を実現するには、各業務の合間に次の不連続な変化を実現するための余剰リソースを生み出す必要がある。また余剰リソースをもって生み出したプランについて、十分な投資を行い、成功するまで突き詰める必要がある。
これらを阻む課題はマネジメント層と現場の2箇所に、それぞれ1つずつ、プラス全体で2つの計4つある。これらの課題を解決することが不可欠である。
マネジメント層における課題:生み出された余剰リソースを将来への投資に振り分ける判断の実現
先例に囚われず、明確なガイドラインに沿った投資および収束の厳密な意思決定が不可欠である。当然ながらガイドライン自体も状況に合わせて見直しす必要がある。
現場における課題:業務の創造化を積極的に行うマインドセットの醸成
常に業務を行う意義を問い続け、定型的になろうとしている業務は積極的に手放す、つまり「オフロード」「ワークアウト」することが不可欠である。
共通する課題1:プランの成功に向けた努力と冷徹な意思決定
当然だが一度決定した投資案件は、成功するか、失敗の条件に合致するまで継続する必要がある。遂行に際しては社内でも適した人材を投入することが不可欠である。従って子細な人材情報の状態的把握と、構造的な人材開発が求められる。
共通する課題2:積極的な外部情報の咀嚼
企業は社会の中で活動するものであり、製品を提供することにより得られる収益は、次世代の製品開発に対する投資である。それを支えるのは社会に溢れるあまたの情報から断片をより集め、咀嚼することでインテリジェンスに変えるための活動が不可欠である。今日不要な情報でも後日別の情報との組み合わせで有意な意味を持った場合、それは業界でも先鋭的なことであり、競争力の強化につながる可能性を持つこととなる。よって現在の価値観での取捨選択を行わず、体系的な咀嚼が求められる。
当然ながらこれらの行動を支える社内評価システム、人材確保と開発ノウハウの獲得と構築は不可欠である。
以上のように余剰リソースを生み出すためには投資が必要である。ここでの投資目的は「将来競争力の獲得」であり、そのための方法は現場業務のオフロードしかない。オフロード先としては社外への業務委託を想像するが、実際にはITシステムを用いる方が再利用性とノウハウ保留の観点から有益である。またオフロードの過程では現場の負荷が増加するため、それを含めての投資を行う必要がある。
「業務の創造化」は簡単ではない
「業務の創造化」は一個人の努力の範囲を超えている。実現のためには会社組織全体での取り組みが不可欠であり、しかも組織体系、文化形態の変革など、困難を乗り越える覚悟が求められる。しかしこの困難があるからこそ、「業務の創造化」による成功は貴重であり、挑戦する価値がある。
参考文献
"Strategy as Transformation", Vijay Govindarajan
「ウイニング 勝利の方程式」 ジャック・ウェルチ

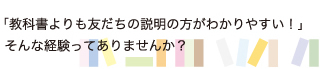

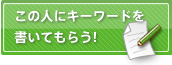





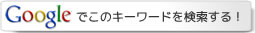
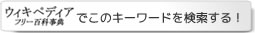

コメントはまだありません