二人は楽しそうに
追々入って来るホールの観客を見降ろしながら、木の入るのを待っていた。
到頭ある日葉子から電報が来た。月蒼く水煙る、君きませというような文句であった。
庸三はもう二週間もそれを待ちかねていた。絶望的にもなっていた。いきなり彼女の故郷へ踏みこんでいって、町中に宿を取って、ひそかに動静を探ってみようかなぞとも考えたり、近所に住んでいる友人と一緒に、ある年取った坊さんの卜者に占ってもらったりした。彼はずっと後にある若い易の研究者を、しばしば訪れたものだったが、その方により多くの客観性のあるのに興味がもてたところから、自身に易学の研究を思い立とうとしたことさえあったが、老法師のその場合の見方も外れてはいなかった。占いの好きなその友人も、何か新しい仕事に取りかかる時とか、または一般的な運命を知りたい場合に、東西の人相学などにも造詣のふかい易者に見てもらうのが長い習慣になっていた。支那出来の三世相の珍本も支那の古典なぞと一緒に、その座右にあった。
「梢を叩き出してもかまわない。おれが責任をもつ。」
そう言って庸三の子供たちを激励する彼ではあったが、反面では彼はまた庸三の温情ある聴き役でもあった。
老法師は庸三たちの方へ、時々じろじろ白い眼を向けながら不信者への当てつけのような言葉を、他の人の身の上を説明している時に、口にするのであったが、順番が来て庸三が傍へ行くと、不幸者を劬わるような態度にかえって、叮嚀に水晶の珠を転がし、数珠を繰るのであった。
「この人は、きっと貴方の処へ帰って来ます。慈父の手に縋るようにして帰って来ます。貴方がもし行くにしても、今は少し早い。月末ごろまで待っていなさるがいい。そのころには何かの知らせがある。」
卜者は言うのであった。
薬学部 進級試験対策 塾
コメント
コメントできません

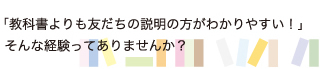






コメントはまだありません