誰もいない体育館
なぜ、あんな所の鍵が開いていたのか、考えてみれば不思議ね。体育館の中にもぐりこんだ私は、天井の近くをぐるりと回る鉄のデッキを走り、その人の立っている真上あたりの窓を、内側から思いきり開いたの。バスケットボールのゴールのネットがはね上げられている所。手すりにつかまって身を乗り出すと、あの人の後ろ姿に手が届きそうな位置だった。コンクリートを吹きつけた崖をはさんで、すぐ下には高架になった新しい特急の線路が一直線に延びていて、この町の全部がその向こうに拡がっているの。遠くには海と、海岸沿いに走る高速道路の橋桁が、透明な朝の光の中で西に向かってゆるやかなカーブを切っていたわ。
気配に振り向いたあの人は私を見つけると、少し悲しそうな目をした。はっきりとした目だったけど、深く落ちこんでいた。目だけじゃなくて身体全体がとても老けて見えて、私より十才以上は年上に見えた。
私に向かってあの人は低い、しゃがれた声で何か言った。うるさい程の蝉の声にかき消されて、私にはそれが聞こえない。
『何? 何て言ったの』
私は手すりから身体を乗り出して叫んだ。
『お人形さん、気を付けな。落っこちるぞ』
あの人はそう言った。水気のない声だった。
『何を見ているの』
私は叫んだ。
私は叫んでばかりいた。蝉の声に負けないためじゃない。この人にはそれぐらい叫ばなくちゃ声が届かないって、その時私はそう決めたから。
『たいした学校だよ、ミス・ロンリー。毎日、ジューサーにかけられているようなもんだろ。何、習ってる? 都市で生き抜いていく方法なんて、誰も教えてくれないだろ』
早口だった。
歌を歌っているように、私には聞こえた。
VALID SEO いまどきのSEO対策 ウィルゲート ヴォラーレ
コメント
コメントできません

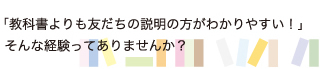






コメントはまだありません